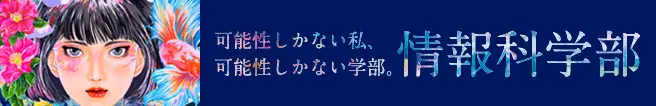ジェネリック医薬品とは何かを簡単に解説!新薬との違いも



この記事について
皆さんは「ジェネリック医薬品」という言葉を聞いたことはありますか?
薬局で「ジェネリック医薬品に変更しませんか?」と聞かれた経験がある方も多いと思います。
しかし、「ジェネリック医薬品は新薬より安いと聞くけれど、本当に効くのかな?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
今回は、ジェネリック医薬品の特徴や、新薬との違いについて詳しく解説します。
実はこの選択は、私たちのお財布だけでなく、日本の医療制度の未来にも関わる重要な決断なのです。
ぜひ最後までご覧ください!
このコラムは、私が監修しました!

教授山下 美妃Yamashita Miki医療薬学
薬剤師は、病気を抱える患者さんの病気の治療や生活者(健康な人)の健康維持に、非常に重要な役割を果たしている職種にもかかわらず、国民にはそれが十分に知られていないのが現状です。
私は、国民に薬剤師の役割を十分に理解してもらい、その価値を高めるために、「薬剤師業務の質を上げること」、「薬剤師の役割を社会に対して“見える化”すること」の2つが重要だと考えています。
薬剤師業務の質を上げるためには、研究データ等のエビデンス(根拠)を活用して、薬剤師業務を行う必要がありますが、これらエビデンスは不足している場合が多いので、私は、このエビデンスの創出に取り組んでいます。
また、薬剤師業務を社会に対して“見える化”するために、薬剤師が患者の病気の治療や生活者(健康な人)の健康維持に関わることで、どのような効果があるのかを研究によりデータ化し、公表するという取り組みを行っています。
目次
 ジェネリック医薬品とは?簡単に解説
ジェネリック医薬品とは?簡単に解説
ジェネリック医薬品とは、新薬(先発医薬品)の特許期間が終了したのちに製造・販売される医薬品です。
新薬と同じ量の有効成分を使用し、品質、効き目、安全性が同等であると国から認められています。
新薬を「先発医薬品」というのに対して、ジェネリック医薬品は「後発医薬品」ともいいます。
ジェネリック医薬品は、新薬に比べて開発費用を抑えられるため、より低価格で提供できることが特徴です。
製品によっては、服用しやすいように大きさや味・香りなどを改良したものもあります。
ジェネリック医薬品のメリット
ジェネリック医薬品を使用することには、主に2つの大きなメリットがあります。
1つ目は、新薬と比べて価格が抑えられていることです。
この価格の違いは、開発にかかる時間と費用の違いから生まれます。
新薬の開発にはおよそ9~17年もの歳月と数百億円以上のコストがかかると言われています。
一方、ジェネリック医薬品は、すでに新薬の開発段階で安全性が確認されたものと同じ有効成分を使用するため、開発期間は3~5年程度で済みます。
したがって、開発にかかる時間と費用を大幅に抑えることができるため、薬の価格も抑えられるのです。
2つ目は、患者さんの利便性を考えた改良が施されているものがあることです。
例えば以下のような工夫があります。
- 錠剤を小さくする
- ゼリー状や液状にする
- 味やにおいを改良する
- 誤飲防止のための色や形の区別をしている
ジェネリック医薬品は、新薬が発売されてから20〜25年程度の期間を経た後に開発・発売される医薬品なので、新薬の使用状況を見た上で、味の改良や小型化など服用しやすさを考えた改良を施せるのです。
 ジェネリック医薬品の世界の使用率
ジェネリック医薬品の世界の使用率
日本でのジェネリック医薬品の使用率は上昇を続け、令和5年7〜9月の数量シェアは82%となっています。
この数字は非常に高いように見えますが、アメリカやドイツなどではジェネリック医薬品の数量シェアは90%以上と非常に高く、世界には日本よりも使用率が高い国があります。
日本も、これらの国々の水準を目指して普及促進に取り組んでいます。
なぜジェネリック医薬品の普及を進めるの?
令和5年度の日本の国民医療費の総額は年間約47兆円にのぼり、年々増加しています。
この国民医療費のうち調剤医療費は約8.3兆円を占めています。調剤医療費の約3分の2は、「薬剤料」、つまり薬代です。
この医療費の多くは、私たち一人ひとりが加入している公的健康保険から支払われていますが、この増え続ける医療費を維持することが難しくなってきている現状があります。
ジェネリック医薬品を利用することで、この薬代が安くなるため、患者さん本人の自己負担金が減るだけでなく、国全体の調剤医療費が下がるため、結果的に、国民医療費の削減にもつながります。
日本の医療保険制度を維持するための施策としても、ジェネリック医薬品の利用が進められているのです。
 ジェネリック医薬品と新薬の違い
ジェネリック医薬品と新薬の違い

ジェネリック医薬品と新薬の違いをより詳しく見ていきましょう。
開発過程の違い
 新薬は、以下の流れ、期間で開発・審査が行われます。
新薬は、以下の流れ、期間で開発・審査が行われます。
- 創薬スクリーニング:2〜3年
- 非臨床試験:3〜5年
- 臨床試験:3〜7年
- 承認審査:1年
- (発売後)再審査:4〜10年
このように多くの試験と、発売後の患者さんへの使用・再審査を経て、効き目と安全性が十分に確認されていきます。
一方、ジェネリック医薬品は、新薬の特許期間終了後、すでに使用実績のある有効成分を用いて作られるため、一部の試験は免除されますが、以下の4つの重要な試験により品質、効き目、安全性をチェックしています。
- 規格試験:有効成分の純度や量を確認
- 溶出試験:新薬と同じように体内で溶けるかを確認
- 生物学的同等性試験:新薬と同じように有効成分が体内に吸収されるかを確認
- 安定性試験:品質が温度や光などの影響を受けず保たれるかを確認
添加剤の違い
ジェネリック医薬品は、新薬と異なる添加剤を使用する場合があります。
そのために味や香りが新薬と異なることも。
ただし、使用される添加剤は安全性が確認されたものだけで、効き目や品質、安全性に違いはありません。
アレルギー体質の方は、新薬・ジェネリック医薬品に関わらず、添加剤について医師や薬剤師に相談することが大切です。
医薬品についてさらに深く理解したい方は、「新薬ができるまでの過程を詳しく解説!」のコラムもご覧ください。
新薬がどのように開発され、私たちの手元に届くのか、その過程について詳しく解説しています。
 ジェネリック医薬品とは、新薬と同じ成分・効き目を持つ後発医薬品
ジェネリック医薬品とは、新薬と同じ成分・効き目を持つ後発医薬品
ジェネリック医薬品とは、新薬と同じ有効成分を使用し、品質、効き目、安全性が同等であると国から認められた医薬品です。
開発コストを抑えることで価格を低く設定できるので、患者さんの医療費負担を軽減できます。
さらに、服用のしやすさや使い勝手を改良するなど、患者さんの立場に立った工夫も施されています。
ジェネリック医薬品と新薬の違いは、その開発過程。
異なる添加物を使うこともあり、味や香りが異なる場合もありますが、有効性、品質、安全性は新薬と変わりはありません。
 北海道科学大学薬学部薬学科で薬学を学びませんか?
北海道科学大学薬学部薬学科で薬学を学びませんか?
北海道科学大学薬学部薬学科の山下 美妃教授は市民向けに「ジェネリック医薬品とは」という講座を行っています。
最近、テレビコマーシャルでもよく見かけるようになった 「ジェネリック医薬品」。
お薬代が安くなるとは聞くものの、 詳しいことはよくわからないのがジェネリック医薬品ではないでしょうか。
講座では、このジェネリック医薬品について「なぜ安いの?」「効き目や安全性は大丈夫なの?」「他のお薬と何が違うの?」など、数々の疑問にお答えします!
北海道科学大学薬学部薬学科は、薬剤師国家試験合格率は87.2%(過去5年実績平均)と、全国平均を上回る高い合格率を誇っており、地域住民の健康を支える薬剤師を育成しています!