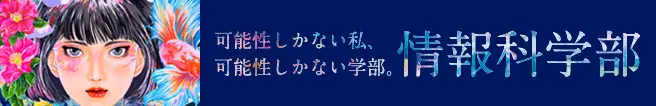新薬ができるまでの過程を詳しく解説!



この記事について
病気やけがの治療に欠かせない医薬品。
新しい医薬品が開発されることで、これまで治療が難しかった病気に対しても、治療の可能性が広がっています。
今では、多くの医薬品が私たちの健康を支えていますが、その開発には長い時間と多くの人々の努力が必要です。
今回は、新しい医薬品ができるまでの過程について、わかりやすく解説していきます。
たくさんの工程と長い時間をかけて新薬が生まれていることを、ぜひ知ってくださいね!
このコラムは、私が監修しました!

教授光岡 俊成Mitsuoka Toshinariレギュラトリーサイエンス
私は薬系技官として厚生労働省での薬事行政を中心に、食品衛生、麻薬取締、内閣府での科学技術政策や生命倫理、社会保険診療報酬審査支払基金での診療報酬審査等、医薬品、薬剤師や薬局が関係するであろうほとんどの分野の行政に32年間関わってきました。
質の高い薬剤師を育成しようとする北海道科学大学での薬学・薬剤師教育に対する熱意に魅力を感じ、転職することにしました。以来、「医薬品の適正使用のための薬剤師と地域薬局のあり方に関するレギュラトリーサイエンス研究」を大きなテーマとしてきました。
レギュラトリーサイエンスとは、科学的方法(仮説、検証、論理的推論等)を駆使して現実社会が直面する課題を解決するための科学的活動のことです。地区薬剤師会等と協力し、医薬品の適正使用のための薬剤師と地域薬局のあり方を提案していきたいと考えています。
目次
 新薬はどうやってできる?
新薬はどうやってできる?
新薬ができるまでの過程には、多くの時間と労力、そして多額の費用が必要です。
日本において、1つの新薬を開発するには、約9~17年もの時間がかかります。
さらに、開発の成功率は約23,000分の1ともいわれており、多くの候補物質の中からごくわずかな物質だけが薬として認められます。
新薬開発の主な過程は以下のとおりです。
- 基礎研究:将来、薬となる可能性のある新しい物質を発見し、製造する段階
- 非臨床試験:動物実験や細胞を使って試験を行う段階
- 臨床試験(治験):人での安全性と効果を確認する段階
- 製造販売承認:厚生労働省による審査を受け、薬として承認される段階
- 製造販売後調査:発売後も継続的に安全性や効果を確認する段階
 新薬ができるまでの過程を詳しく解説
新薬ができるまでの過程を詳しく解説

新薬開発の各段階について、詳しく見ていきましょう。
基礎研究(2~3年)
基礎研究では、将来、薬となる可能性のある新しい物質を見つけ出します。
研究者たちは、以下のような方法で新薬の候補となる物質を探します。
- 天然素材(植物・動物・微生物など)からの発見
- 科学技術を用いた新しい物質の製造
- 2つ以上の物質の組み合わせ
- 最新の科学技術の活用
見つかった物質は、時間をかけて調べられ、薬になりそうなものだけが選び取られます。
非臨床試験(3~5年)
非臨床試験では、基礎研究で選ばれた新しい物質について、動物や培養細胞を用いる試験などで、医薬品の薬効と副作用 (毒性) の関係を調べます。
また、同時に治験薬としての品質や安定性も調べます。
これらの試験の情報から臨床試験デザインを検討します。
臨床試験(治験)(3~7年)
臨床試験は、実際に人での効果と安全性を確認する重要な段階です。
必要な非臨床試験を通過した薬の候補(治験薬)が、人にとって安全で効果があるかどうかを確認します。
治験は、法律に従い、多くの専門家による検討や審査に基づいて行われます。
以下の3段階に分かれて実施されます。
- 第1相試験:少数の健康な人を対象に、安全性の確認
- 第2相試験:少数の患者を対象に、効果的で安全な投与量・投与方法の確認
- 第3相試験:多数の患者を対象に、これまで使われてきた薬などとの比較
承認申請・製造販売(1~2年)
各種試験で有効性、安全性、品質などが証明されたあと、厚生労働省に新薬として製造・販売するための承認申請を行います。
その後、学識経験者などで構成する薬事・食品衛生審議会などの審査を受け、「薬」として認められると、製造販売することができます。
製造販売後調査(6カ月~10年)
医療機関で多くの患者に使用しながら、開発段階では発見できなかった副作用や適正な使い方に関する情報なども調査し、製薬企業の医薬情報担当者(MR)によって収集されます。
新薬は発売後もさまざまなチェックが義務付けられているのです。
 新薬ができるまでの過程を知り、医薬品の理解を深めよう
新薬ができるまでの過程を知り、医薬品の理解を深めよう
新薬ができるまでの過程は、基礎研究から始まり、非臨床試験、臨床試験を経て、最終的に国の承認を得るまで、9~17年という長い時間をかけて慎重に進められます。
約23,000分の1という低い成功率の中で生まれる新薬は、多くの研究者の努力によって支えられ、人々の健康を守る重要な役割を担っています。
新薬は発売後も継続的な調査が行われ、より安全でより使いやすい薬への改善が行われています。
 北海道科学大学薬学部薬学科で薬学を学びませんか?
北海道科学大学薬学部薬学科で薬学を学びませんか?
新薬開発には多くの時間と専門的な知識、そして何より情熱が必要です。
北海道科学大学薬学部薬学科では、新薬開発に関わる研究者や、医療現場で薬を適切に患者さんに届ける薬剤師など、医療に携わる専門家の育成に力を入れています。
薬学教育モデルのコアカリキュラムに加え、独自のカリキュラムを展開し、創薬研究や公衆衛生の担い手として地域の健康を支える薬剤師の育成に注力しています。
新薬開発や薬学に興味のある方は、ぜひ北海道科学大学薬学部薬学科のオープンキャンパスへ!