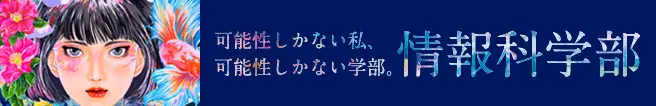なぜ紫外線を浴びると日焼けするのか?



この記事について
日差しの強い夏はもちろん、真冬のスキー場でも日焼けをします。
日焼けの原因は太陽光に含まれる紫外線です。
そこで今回は、なぜ紫外線を浴びると日焼けするのかについて解説します。
光とは何か、紫外線を浴びたときと紫外線以外の光を浴びたときとで何が違うのかということから、紫外線から肌や目を守るにはどうすればよいのかということまでを解説します。
このコラムは、私が監修しました!

教授内田 尚志Uchida Takashi物理学
私の専門分野は物性物理学で、金属の磁気的性質の理論的研究を行っています。磁気的性質を示す金属の場合、金属を構成する原子自身が磁石になっていて、これを磁気モーメントと言います。原子の磁気モーメントは主として原子内部の電子の磁気モーメントにより形成されます。私の研究においては、金属中の電子の状態をコンピューター上で再現することにより、原子の磁気モーメントにより形成されるミクロな磁気構造の解明を目指しています。最近は、特定の金属において、原子の磁気モーメントが特殊な渦構造を形成することが見いだされ、次世代記憶素子への応用の可能性も指摘されていることから、私の研究においても、金属中で形成される特異な磁気構造とその物理的な起源の解明を目指しています。
私は普段、大学においては、主として工学部や保健医療学部の物理学の授業を担当しています。できるだけ分かりやすい授業を展開することにより、受講する学生の皆さんが物理学に興味・関心を持って勉強してくれるようになることを目指しています。
私が物理学に興味を持ったきっかけは、小学5年生のときに、電子部品を専門店で買い集め、初めてトランジスタ・ラジオを自作した経験にあります。設計図通りに組み立て、スピーカーから音が聞こえてきたときは大変感動しました。放送局から放たれた電波に音声情報が載せられ、その電波が何もない空中を伝わり、自分のラジオのアンテナがその電波を受信し、音声を再現できることは驚異的であると思いました。そして、物理を一生懸命勉強すれば、どういう仕組みで電波が発生し空間を伝わるのか、受診した電波がどのようにしてラジオが捉え増幅し音声に変えるのかということが理解できることを知り、将来は物理を専門に学びたいと考えました。私は大学での授業以外に、大学が主催する講座で小学生、中学生、高校生に物理を教える機会もあります。物理を学ぶ面白さや感動を多くの若い人たちに味わってもらいたいと考えています。
目次
 そもそも日焼けの原因「紫外線」とは?
そもそも日焼けの原因「紫外線」とは?
紫外線とは電磁波の一種で、電磁波とは電場(でんば)と磁場(じば)が振動しながら伝わる波です。
電場はその名の通り、電気と関係する物理量です。
物体が電気を帯びるとき正と負の2種類がありますが、これらをそれぞれ正の電荷(でんか)、負の電荷(でんか)といいます。

空間に正または負の電荷があると、そのまわりには電場が生じています。
その電場の中に第二の電荷を置くと、第二の電荷は第一の電荷がつくる電場から電気力を受けます。
また、第二の電荷もそのまわりに電場をつくるため、第一の電荷も第二の電荷のつくる電場から電気力を受けます。
このようにして、電荷と電荷が力を及ぼし合うときは電場を介して電気力が作用します。

電気力とよく似ているのが磁石の磁極の間に働く磁気力です。
磁極と磁極が磁気力を及ぼし合うとき、磁極が磁場をつくり、その磁場が相手の磁極に磁気力を及ぼすという形で、磁場を介して磁気力が作用します。


電場のことを電界(でんかい)、磁場のことを磁界(じかい)ともいいます。
電場と磁場については、電場が変化すると磁場を生じ、磁場が変化すると電場を生じるという法則があります。
そこで、例えば、電荷を帯びたものを振動させると、それによって電場が変化し、変化した電場が磁場を生み、新たに生じた磁場が電場を生みという形で、電場と磁場の生成が繰り返されながら空間を伝わっていきます。
これが電磁波です。

すべての物質は原子からできていて、原子はさらに正の電荷を持つ原子核と負の電荷を持つ電子からできています。

私たちの身の回りにある物質の中では原子は熱振動をしているため、正の電荷を持つ原子核と負の電荷を持つ電子が振動し、このため、人間を含めて身の回りのすべての物質は電磁波を出しています。
ただし、室温程度の物質は主として目に見えない赤外線を放出しています。
身の回りの物質が色づいて見えるのは、太陽光や照明の光の反射光の色が見えているのであって、物質自身が可視光線を出しているわけではありません。
一方、太陽の表面温度は約6000℃であり、太陽表面では6000℃に対応した電子等の熱振動により電磁波(太陽光)が発生し、赤外線だけでなく可視光線や紫外線まで含む電磁波が地球まで到達し、地球上の生命活動を維持する上で重要な役割を果たしています。
電磁波は、進行方向に垂直に電場が振動し、電場と垂直な面内で進行方向に垂直な方向に磁場が振動しながら空間を伝わっていきます。

周期的に変化する波の山から山までまたは谷から谷までの距離を波長といいますが、電磁波は波長の長い方から順に、電波、赤外線、可視光線、紫外線、エックス線、ガンマ線という名称で分類されています。
ただし、エックス線とガンマ線には波長領域に重なりがあり、電子の状態変化によって発生する場合をエックス線、原子核の状態変化によって発生する場合をガンマ線として区別しています。
このうち、目で見ることができる電磁波が可視光線です。
人間は、波長の異なる可視光線を異なる色の光として認識します。
可視光線は波長の長い順に赤、橙、黄、緑、青、藍、紫となります。
赤よりも波長が長い光が赤外線、紫よりも波長が短い波が紫外線で、これらの光は目に見えません。
紫外線と赤外線は、可視光線の紫と赤のそれぞれ外側にあることから「Ultra Violet(UV)=紫外線」「Infrared=赤外線」と呼ばれています。

なぜ紫外線で日焼けが起こるのか?
光は電磁波という波として空間を伝わっていきます。
このため、異なる光の波が出会うと、波の山同士や谷同士が重なって光を強め合ったり、波の山と谷が重なって光を打ち消し合ったりします。
このような現象を光の干渉(かんしょう)といいます。
例えば、シャボン玉が色づいて見えたりするのは、いろいろな波長の光が干渉により強め合ったり弱め合ったりすることが原因です。

このように光が波の性質を示すことは数多くの実験から分かっているのですが、光が物質に吸収されるときは決まったエネルギーをもつ粒子(りゅうし)として吸収されることが分かっています。
この光の粒子のことを光子(こうし)といいます。
光子のエネルギーは光の波長に反比例します。
つまり、波長の長い光の光子のエネルギーは小さく、波長の短い光の光子のエネルギーは大きいのです。
例えば、赤外線は可視光線より波長が長いため、光子のエネルギーは比較的小さく、赤外線が皮膚に当たっても赤外線の光子が皮膚の組織を損傷することはありません。
したがって、輻射式の電気ストーブのそばで長時間を過ごしても、日焼けすることはありません。

この場合、ストーブの近くにいるほど体が暖まるのは赤外線の光子がたくさん皮膚に当たるからであって、数は多くても赤外線の光子1個1個のエネルギーは小さいため、皮膚の組織が損傷することはないのです。
一方、紫外線は可視光線よりも波長が短いため紫外線の光子のエネルギーは大きく、紫外線の光子が皮膚に当たると皮膚の組織を損傷し、日焼けすることになります。
夏は特に紫外線量が多いため、紫外線の光子が大量に降り注ぐことになり日焼けしやすいのです。
また、真冬でも雪が積もっている場所では雪が紫外線を反射するため、日焼けをしやすくなります。
真冬のスキー場にいる場合、太陽光を浴びていてもストーブのそばにいるときと比べて皮膚に当たる光子の総数が少ないため体はほとんど暖まりませんが、太陽光には紫外線が含まれていて紫外線の光子1個1個のエネルギーが大きいために、日焼けしたり、目が紫外線で赤目になったりします。
このため、スキー場では目を守るためにゴーグルの着用は必須です。
さらに、ゴーグルで覆われていない部分を守るために日焼け止めも塗った方が無難です。
このように紫外線の光子のエネルギーは大きく人間の肌や目を傷める作用があるのですが、光子のエネルギーが大きいために人間にとって有害な細菌を殺す殺菌作用もあります。
温泉などでおしぼりや櫛などの紫外線殺菌装置を見たことがある人も多いかと思います。
また、夏の晴れた日にふとんを天日干しするとよいのも、紫外線の殺菌作用があるからです。
紫外線の波長とは?
紫外線の波長は100〜400nm(ナノメートル ※1nm=100万分の1mm) です。
また、紫外線(UV)は波長の長さによって、さらに以下のように区分されます。
- UV-C (100〜280nm):オゾン層で吸収されるため、地表に届かない
- UV-B (280〜315nm):ほとんどがオゾン層で吸収されるが、地表に届く10%程度が日焼けの原因になる
- UV-A (315〜400nm):地表に到達する紫外線の約90%を占め、日焼けの原因になる
紫外線から肌や目を守るにはどうしたらよいか?
紫外線の中でUV-Cは波長が最も短く光子のエネルギーが大きいため、UV-Cを長時間浴びると遺伝子を損傷するなど、生物に大きな影響を与えます。
UV-Cは地球大気の上層部のオゾン層で吸収されるため地上には本来届かないのですが、かつて冷蔵庫の冷媒としてフロンガスが使用されていたことがあり、フロンガスがオゾン層を破壊しオゾンホール(オゾン層にできた穴)が広がり、このことが原因で地上にもUV-Cが降り注いでいることが問題となり、フロンガスの使用が禁止されることになりました。
オーストラリアではオゾン層の薄さが懸念されているため、紫外線に対する積極的な取り組みが進められています。
子どもたちが外へ出るときには、「長袖のシャツを着る」「日焼け止めを塗る」「帽子をかぶる」「サングラスをかける」といったスローガンが打ち出されています。
これらの対策は、もともと地上に到達する紫外線であるはUV-B、UV-Aに対しても有効です。
日傘をさすのも有効です。
日焼け止めには紫外線を吸収して防ぐ「紫外線吸収剤」と、紫外線を反射して防ぐ「紫外線散乱剤」の2種類があります。
いずれの日焼け止めを用いた場合も紫外線の光子が肌の奥深くに届くのを防ぐことが目的ですので、日焼け止めはある程度厚く肌に塗る必要があります。
紫外線以外の電磁波の影響は?
紫外線よりも波長の短い電磁波としてエックス線があります。
エックス線の光子のエネルギーは非常に大きいため、人体にエックス線を照射させたときは、骨や組織の病変部等、高密度な部分以外は透過してしまうため、エックス線写真で骨が骨折しているかどうかを調べたり、肺の組織が病変で硬くなっていないかどうか等を調べる目的で、医療の分野で用いられています。
このように現代の医療ではエックス線診断は欠かせないものですが、エックス線の光子のエネルギーが非常に大きいために、人体の遺伝子を破壊する威力があり、エックス線を短時間に大量に浴びるとがんを発生する危険性があります。
このため、患者および放射線技師の双方に被ばく量の上限が定められていて、これを厳守する必要があります。
 基盤能力を養う北海道科学大学の全学共通教育部
基盤能力を養う北海道科学大学の全学共通教育部
北海道科学大学の全学共通教育部は、社会で必要となる基盤能力を養う教育や英語、数学、物理等の基礎教育を担当しています。
大学卒業後に社会で活躍するためには、専門分野を深く学ぶのはもちろん、社会人として必要な教養と幅広い見識を養うことが大切です。
北海道科学大学では、すべての学部・学科の学生が学ぶ基盤能力育成プログラム「HUSスタンダード」において、4つの力を身につけることを目指しています。
4つの力とは、①コミュニケーション力 ②課題発見解決力 ③自らを律し学び続ける力 ④多様な視点から物事を捉え、異なる意見を理解する力です。
日焼け止めの仕組みのような身近な疑問から課題を見い出し、解決していく姿勢は、さまざまな問題解決能力の育成につながります。